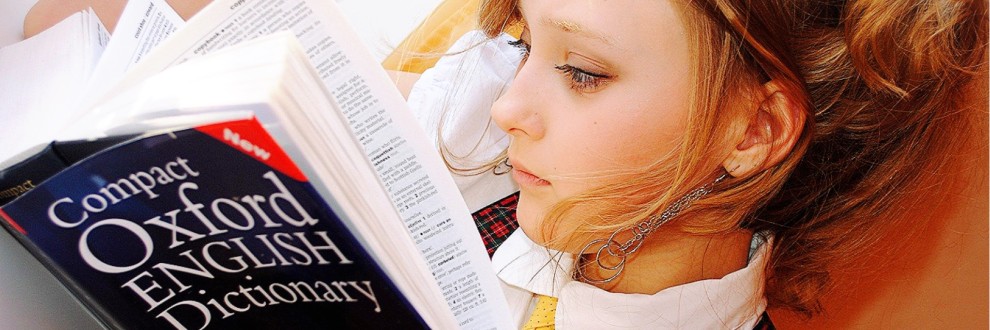「私のなかの彼女」1月の短編ファンタジー
1
みんなが私を見ている。
「悠人君のお母さん」でもなく「美哉ちゃんママ」でも「木原さんの奥さん」でもなく、「水城ゆう」として。
「水城ゆう」はペンネームだ。本名は木原優香。38歳、二人の子持ちのパート主婦。何も取り柄もない変凡な人間だったのに、今まさにS文学新人賞受賞者として挨拶するのを心臓をバクバクさせながら待っている。まさか、こんなことが私に起こるなんて思ってもいなかった。
小説を読むことは学生時代から好きだった。けれど子どもが生まれてから小説なんて読んでいるひまはなかった。子育てと家事、パートで疲れて、あいた時間に電子漫画やネット配信のドラマを見るくらいがせいぜいだった。
それが去年交通事故を起こしてから、なぜか小説を書きたくてしかたがなくなった。それまで小説など一度も書いたことがなかったのに。いや、ブログでさえ書いたことがなかった。
それがいきなり書きたい衝動にかられ、子どもたちを寝かしつけた後、眠い目をこすりながらノートパソコンを開いた。ノートパソコンも自分の貯金で安いものを買ったのだ。そうして書き上げた小説を、ためしにこのS文学新人賞というものに送ってみた。原稿用紙にしておよそ300枚も自分が書けるなんて思わなかった。他の小説に劣っているようにも思えなかったし、なにしろこんなことはもう二度とできないような気がした。交通事故で頭を打って何か脳の仕組みでも変わったのだろうか。とにかくこの小説を無駄にできないと思った。まさかそれが、いきなり新人賞を受賞してしまうとは。
「それでは、新人賞受賞の水城ゆうさんにご挨拶をお願いします」
司会者がにこやかに優香をうながした。
優香は立ち上がり、震える足で中央のマイクに向かった。
授賞式の10ヶ月後に、優香の小説は単行本となり書店に並んだ。近くの駅ビルの本屋に行ってみると、小説のスペースに○○文学新人賞という帯をまとって平積みされていた。さすがに有名な賞だけあった。ふるえる指で一冊手に取ってみる。
「水城ゆう」私が書いた本だ。新人賞受賞の電話をもらった時から、ずっと夢の中にいるかのようだ。本を戻して、スマホで写真を撮る。一冊で消える作家は多いと言われた。もしかしたら、もう二度とないかもしれない。これが私の人生の頂点かもしれない。
名残惜しくその場に10分以上立っていたが、そろそろ帰らなければならない。スーパーで買い物をして、夕飯を作らなければ。
歩き出そうとした時、ふいに腕をつかまれた。
ぎょっとして振り返ると、50代前半くらいの女性が優香の腕をつかんでいた。何か怖いくらいの必死な形相だ。
「え? あの?」
「木原優香さんですよね」
「え? どうしてそれを?」
新人賞を主催している文芸雑誌や出版社のネットに顔写真は出ていた。本名も出ていただろうか。けれど出ている写真はきれいにヘアメイクしたものだ。パート帰りの優香はかなり雑な格好をしていた。
「少しお話よろしいですか?」
「いえ、急いでいますので」
「『私のなかにいる彼女』は、あなたの作品じゃないですよね?」
「え、どういうことですか?」
さすがにむっとした。パートで疲れてこれからスーパーに買い物に行かなくちゃならないのに、見知らぬ女性が腕をつかんできて「あなたの作品じゃない」とはどういうことだ。盗作だとでも言いたいのか。
優香は書き上げた小説を締め切りが近く枚数が合っていた新人賞に送ったのだったが、S文学新人賞は小説家への登竜門と言われている賞だった。注目されるぶん、応募者による5チャンネルもできていた。まだ優香の悪口は書かれていなかったが、これまでの流れからするといずれ書かれるだろう。ネットレビューでも。
けれどまさか、本屋に並んだ早々こうしてリアルに腕をつかまれ盗作だと言われるとは。
「離してください」
優香は腕を振り払おうとしたが、女性は優香の腕をぎゅっと握っていた。
「いいかげんにしてください」
どうしよう、店員さんを呼ぼうか。有名な作家にはストーカーもいると言うけれど、優香はまだ本を一冊出したばかりだ。もしかして、賞に応募して落ちた人だろうか。落ちて悔しくて逆恨みということなのかもしれない。なんにせよ、この腕のつかみ方、必死の形相は普通ではない。
でも、この人、どこかで見たような?
思い出せそうで思い出せない。まるでついさっきまで覚えていた夢を、まったくといって思い出せないかのように。けれどどちらにせよ、この種の人間と関わるべきではない。店員さんに言おう。優香が無理にでもレジに向かおうとした時、女性が言った。
「『私のなかにいる彼女』は娘が書いていたものです。水城ゆうは娘のペンネームでした」
娘? そんなこと、いくらでも言えるじゃないのと優香が思っていると、女性は優香の腕を握りながら反対側の手で紙袋をこちらに寄こした。片方の取っ手をこちらに向けて開いた紙袋に、ワープロで印字した原稿の束が入っているのが見えた。
私のなかにいる彼女 水城ゆう
原稿用紙の表紙にはそう書いてあった。
「これが証拠だっていうんですか? 本を買って書き写せますよね?」
「そんなことは無理よ」
確かに今日書店に並んだはずだから、全部書き写すのは厳しいだろうけれどできなくはない。今だとスキャンもできるのではないだろうか。
「もう書店に並んでいるんだから、朝買えば無理じゃないですよね」
「無理なんです」
その声は悲しそうに響いた。
「娘は二年前に死んだから」
続きは「フォロワー」「無意識からの言葉」プランでどうぞ。
「フォロワー」「無意識からの言葉」プランなどの入り方はこちらクリック
フォロワー以上限定無料
今すぐフォローをどうぞ! ①詩・エッセイ・雑感など。 ②上位プランの進歩状況などのお知らせ。
無料
【 1000円 】プラン以上限定 支援額:1,000円
このバックナンバーを購入すると、このプランの2023/01に投稿された限定特典を閲覧できます。 バックナンバーとは?
支援額:1,000円