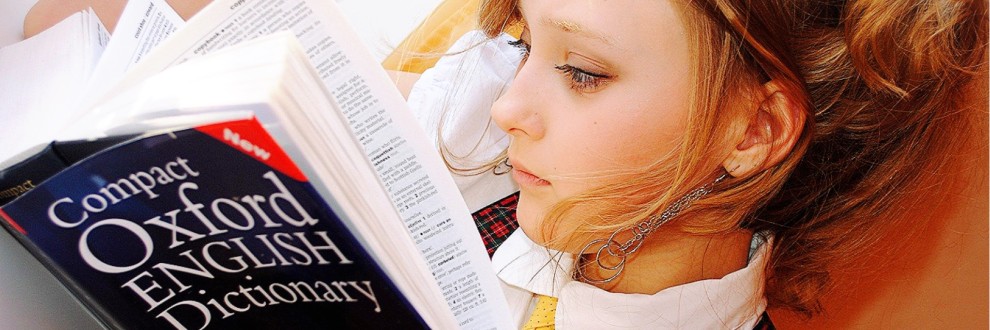「くるくる回る花火」~7月の短編ファンタジー
1
花火の音がぽんぽんとする。
想子は最後に花火を見たかったけれど、いろんな管を通された身体はもうどこも動かなかった。
目を開けることさえ難しい。
たとえなんとか目を開けたことができても、病室の窓のカーテンを開けてと言うこともできないし、窓のそばに行くこともできなかった。
娘と息子がそばにいて、手をにぎり声をかけてくれていた。
92歳になる私の最期を見届けるために。
ああ、これまでいろんな花火を見たなあ。
まぶたの裏にこれまで見た花火を思い浮かべている時だった。
まぶたの裏で、花火がくるくるっと回った。
くるくる くるくる
目が回りそうだと思った時、想子は空に上がった花火を見ていた。
急に、もわっとした夏の夜の熱された空気が身体を包みこんだ。
「ゆうみちゃん、見える?」
若い女の人の顔がまじかにあった。
ああ、この人はお母さんだったと思いだしたとたん、優未(ゆうみ)としての自分を思いだした。
そのとたん、想子としての自分がだんだんと消えていく。
あれ、あんなにはっきりと「想子」を覚えていたのに。
一秒たつごとに、「想子」はかすみのように消えていき、十秒たった時にはもう名前も思いだせなかった。
3歳になる優未は若い父親に抱っこされ、母親がそばで優未の顔をのぞきこんでいた。
ぱんっと赤い花火が空に上がった。
広がっていき、消えていった。
「きれいねえ、ゆうみちゃん」
母親も空を見上げて言った。
優未は着せられた浴衣が汗で首の後ろにはりつくのを感じながら、なんだかすべてが夢のようだと思った。
自分のあやふやさに怖くなって、父親の胸にぎゅっとしがみついた。
「どうした? 音が怖いか?」
父が優しそうに聞く。
「眠くなったのかしらね」
と母。
ああ、違う、そうじゃない。
でもこの感覚をどう伝えたらいいんだろう。
優未は新しく上がった花火の音を聞きながら、一人とまどった。
続きは「フォロワープラン」(無料)「無意識からの言葉」(有料)プランでどうぞ。
「フォロワー」「無意識からの言葉」プランなどの入り方はこちらクリック
フォロワー以上限定無料
今すぐフォローをどうぞ! ①詩・エッセイ・雑感など。 ②上位プランの進歩状況などのお知らせ。
無料
【 1000円 】プラン以上限定 支援額:1,000円
このバックナンバーを購入すると、このプランの2023/07に投稿された限定特典を閲覧できます。 バックナンバーとは?
支援額:1,000円