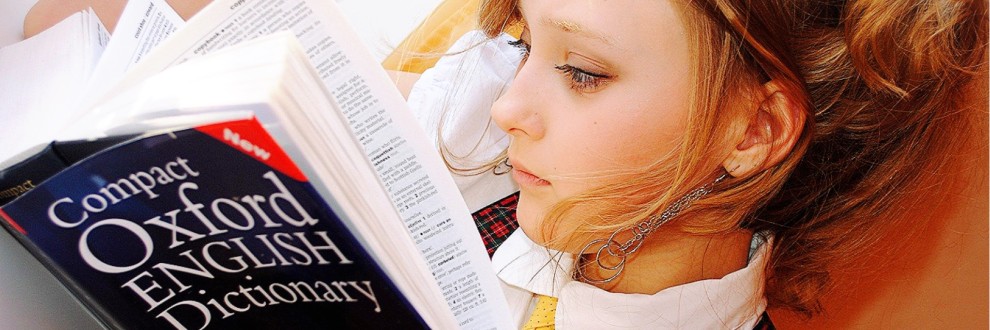「白木蓮」〜6月の短編ファンタジー
1
香苗の両手は、何かをつかもうと幾度も幾度も空を切った。やり続けさえすれば、何かをつかめるとでもいうように。
けれどそんなことは、0.01パーセントの確率もなかった。二人は、煙になって空に上ってしまったのだ。その手にもう2度とつかむことはできない。
何もつかめない絶望とともに、香苗は今日も目覚めた。カーテンのすきまから差し込む晩秋の日差しが、手の甲に当たっていた。まだ38歳なのに筋が目立ち、まるで老婆の手のようだ。ああいやだな、と香苗は眉をひそめた。日の光が憎かった。何もかもが憎かった。
時計を見ると10時を回っていた。夫は会社に行ったのだろう。
申しわけないと思う気持ちさえ起こらない。日常をコツコツと積み上げていく気力などもう1ミリもなかった。
いったい何がいけなかったのだろう。
香苗は凉太と早紀の成長を願っていた。2人の成績を上げることに、自分の承認欲求がなかったとはいえない。けれど普通の範囲内だ。自分のことを後回しにして子育てをするなか、そのくらいの欲を持ったことでこんな罰がくだされるなど誰が思ったろう。
その薬は初め、認知症の薬としてアメリカで開発された。あれよあれよと世界で承認され、日本でも政府が高齢化対策として率先してその薬の投与を推進していった。異例のことだっったが、先進国での認知症問題は大きくなっていた。AIの進化を受け、AIのシュミレーションによって動物実験、人体実験の簡素化がWHOで認められ数年たっていた。
認知症のある家族を持つ者たちは、争うようにその薬の投与予約をした。数が十分ではなかったからだ。けれどそのうち供給量が多くなり、認知症ではない老人たちにも投与券が届くようになった。
そして半年もたつと、その薬は認知症を改善するだけではなく子どもたちの知能も上げると言われるようになった。その情報に、世の母親たちの目の色が変わった。子どもたちの分も予約できるようになると、予約サイトは幾度もパンクしてサーバーが落ちたほどだった。
もちろん香苗も、家事パートそっちのけで予約に夢中になった。
「おい、副作用もあるみたいだぞ」
慎重派の夫の言葉など、ただの雑音でしかなかった。
「何言ってるの? この薬で知能が平均15パーセント上がるのよ。
みんなの知能が15パーセント上がるのにうちだけ飲まなかったら、凉太や早紀の成績は15パーセントも下がることになるの。
何のために高いお金を出して塾に入れてるのよ。塾にだってついていけなくなるわ」
その薬の投与の予約が2人分とれた時には、香苗は天にも昇る気持ちだった。特に高校受験生の凉太にとっては、大吉といってよかった。まだ20パーセントの子どもしか予約がとれないのだ。受験時にもこのままだったら、凉太はあきらめていた県立一位の高校に受かるかもしれない。
ママ友のライングループから嫌がらせをされたけれど、そんなことはなんでもなかった。いくらでも嫉みなさいよ。香苗は有頂天だった。
香苗は凉太と早紀を薬の投与会場にすぐさま連れていった。夫は「もう少し様子を見たほうがいいんじゃないか」とまだ言っていたけれど、様子を見ているうちに受験は終わってしまう。
そんなだから出世しないのよ。20パーセントの子どもしか予約がとれないのに、うちは2人とも投与できる。凉太と早紀の未来は明るいわ。香苗はその未来を信じて疑わなかった。
凉太と早紀が、薬の副作用で苦しみ出したのは速かった。けれどもともと高熱がでたり頭痛などの副作用が出ると言われていた。香苗はそんなものだと高をくくっていた。知能が15パーセントも上がるのだ。高熱くらい出るだろう。頭痛くらい出るだろう。
小学6年生の早紀の副作用はひどかった。医師のもとで薬を飲んだ次の日に全身にけいれんが出、歩けなくなった。けれど薬を投与した医師は何の対処もできず、大学病院を紹介されいろいろな検査をされた。原因はわからなかった。
そんななか凉太は、県立一位の高校に合格した。その嬉しさに、早紀のことはそのうちなんとかなるだろうと甘い見通しを持った。
けれどそれは甘かった。早紀は、日ごとにあちこち身体が痛むと言い出した。立ち上がることもできなかった。
「痛い、痛い」
香苗は早紀の看病のためにパートを辞めた。早紀は夜も身体中の痛みで眠れず、「痛い、痛い」とうめいた。
医者は原因がわからないと言い、ついには精神的なものかもしれないと精神科をうながされた。早紀は小学校の卒業式にも中学校の入学式にも出ることができなかった。凉太が県立一位の高校に入学したことだけが救いだった。
けれどそのうち、凉太も痛みを訴えるようになってきた。
「凉太まで!?」
香苗はその事実を受け入れたくなかった。
「せっかくS校に入ったんだから、がんばって」
病院で原因がみつからなかったこともあり、香苗はつい凉太を頑張らせようとしてしまった。そうして体育の授業中に凉太は倒れた。
それからはあっというまだった。
家の中は、2人の「痛い、痛い」といううめき声ですきまなく満たされた。香苗は、2人の身体をさすってあげることしかできなかった。2人の悲痛な声を聞きながら、まるで悪い夢でも見ているようだった。健康だった子どもたちが痛みで身体をのけぞらせている光景に、お腹の内側がぐわんと揺れ空間がゆがんで見えた。
「だから言ったんだ」
ついに、夫が耐えきれずに言った。
「もう少し様子をみたほうがいいって」
その通りだった。その通りすぎて香苗は夫を責めるしかなかった。
「だったら、もっと強く言ってくれたら良かったじゃない! なんでもっと強く私を止めなかったのよ!」
理不尽なことを言っているなどと思うゆとりはなかった。誰かを責めずにはいられなかった。何かを責めずにはいられなかった。
そうこうするうちに、薬の投与による副作用で世界で死者が出るようになってきた。日本でも死者が何人も出た。さらには、認知症患者に投与されていた時から死者は出ていたという情報も出始めた。
いったいどういうことなの? なぜ最新の効果の高い薬で人が死ぬの? 認知症患者に投与されていた時点で死者が出たのなら、なぜ薬はストップにならなかったの?
香苗の理解が追いつかないうちに、早紀が死んだ。痛みを訴え出してわずか三ヶ月だった。
そうして後を追うように、その一ヶ月後に凉太が死んだ。
2人は痛みが出てから亡くなるまで休むまもなく毎日毎日、「痛い、痛い」とうめき続けた。
健康だった2人の健やかな未来を、香苗は奪ってしまったのだ。
薬を投与した医師を憎んだ。原因をつきとめられない医師たちを憎んだ。薬の投与を推進した政府を憎んだ。薬を作った製薬会社を憎んだ。世界を憎んだ。
「フォロワー」「無意識からの言葉」プランなどの入り方はこちらクリック
フォロワー以上限定無料
今すぐフォローをどうぞ! ①詩・エッセイ・雑感など。 ②上位プランの進歩状況などのお知らせ。
無料
【 1000円 】プラン以上限定 支援額:1,000円
このバックナンバーを購入すると、このプランの2022/06に投稿された限定特典を閲覧できます。 バックナンバーとは?
支援額:1,000円